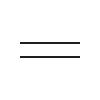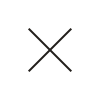NEWS
ロシア文学にハマる日々2025.06.28
こんにちは。矢野です。
先にお知らせ。
シーズナルビーンズ「ケニア マリミラAB」が販売中です。

焙煎は浅煎り。
アプリコットやレッドカラントなどベリー系の甘酸っぱい爽やかでフローラルな酸味感と黒糖のような少しスパイス感のあるまったりとした甘味が特徴的です。
ケニア特有のトマト感も少し感じるものの、全体的なカップイメージとしては口当たりが良く上品な飲み心地で飲み手を選ばず召し上がっていただけると思います。
オンラインショップ及び各店舗にて販売中です。
https://laughter-coffee.com/product/product-8836/
夏限定メニューがスタートしています。
ダルメシアンコーヒー(飲むコーヒーゼリー)

アフォガート

極みコーヒー牛乳

去年も大人気だった夏季限定メニューたち。
早くも販売スタートしてますのでぜひこのちょっと暑くなってきた季節にひんやりしにきてください。
梅雨が明けたみたいですね〜
例年なら降ってるか降ってないかは置いといて、一応祇園祭の最後の方7月半ばくらいでゲリラ豪雨がやってきて祇園祭が終わると同時に梅雨も明けるみたいな感じですが、本当に梅雨が明けたんだとしたら今年はえらく早かったですね。
ほんと大丈夫かと思うことが多い最近です。
今や地球温暖化ではなく地球沸騰化なんて言われていますが、ほんとに世界中で干ばつが相次いでいるようで沸騰化という表現はあながち間違っていないかもしれません。
人間一人一人が当事者意識を持って具体的なアクションを起こしていかなければいよいよどうにならないところまで来ていると思います。しかしなかなかある意味性善説に基づいたような感情任せの啓蒙では人は動かないと思うのでやはり日常生活の延長で勝手にグリーンアクションに繋がっていくような仕組みづくりが必要なんでしょうね。
実は現在でもそういった動きは街づくりなど様々なところに取り入れられているので興味のある方は調べてみても面白いと思います。意外に「そんな技術あったんだ」みたいな発見があったりしますよ。
でも中にはその技術、システムを使用するために前段階でかなりのエネルギーを消費してたりする場合があったりエコビジネスみたいになってるところも多いので情報には精査が必要である点は変わりませんが。
さて前段が長くなってしまってもはやそっちが本題ということでいいのではと思っていますが笑、最近トルストイの「人生論」という本を読みました。ドストエフスキーの「罪と罰」に続きロシア文学にハマっている最近です。そして今はまたドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」を読み始めました。こちらはかなり長編でここまでの長さのものを読むのは初めてなので僕も挑戦ですが、とても楽しみです。
ロシアというお国柄か「本能と理性」「革命と民衆」みたいな一種独特の共通した色があってその退廃的な美学、文学感が僕にはどハマりしているのですが、こんなものばかり読んでいるとファシストだと思われかねないのでそこはしっかりと否定しておきます。笑
僕は無心論者であり根っからの平和主義者ですので。
ただ日本にはない世界のそういった土着的な感覚に触れるのはそれ自体もすごく面白いですし、またそこから日本ならではの良さに気づけたりもして、世界の国々に触れれば触れるほど日本が好きになります。
そんな中で文学にはその国の色みたいなものがより濃く出るような気がします。書かれている背景年代によってその国の雰囲気自体もすごく窺い知れますし、西欧にある大国ポーランドは今までに3度国が消滅しています。ドイツとロシアという大国に挟まれ、時代に翻弄された国であり、かの有名なアウシュビッツ収容所があるのもポーランドです。ナチスはドイツのイメージが強かったので僕はてっきりアウシュビッツもドイツにあるものだと思っていたらあれはポーランドだったんですね。ホロコースト含めユダヤ人が虐殺された人数が多いのも実はドイツではなくポーランドやロシアの方が多いんです。
そんなポーランドは土地柄ポーランド人という人種は厳密にはなく、ユダヤ人やスラブ人、ロシア人やドイツ人など様々な人種が集まってポーランドという国として独立しポーランド人が確立されたわけですが、前述のように3度国として無くなっているのですが、その度にまた独立を果たし今日までポーランドという共同体を維持してきました。僕はこのそんな状況においても維持されてきたポーランドにおける共同体意識に今すごく興味があっていろいろ調べたり本を読んだりもしてるのですが、どうも詩や文学といった言葉がそれを紡ぎ続けてきたという見方が濃厚なようです。
このことからも文学がその国を窺い知るのに非常に有効であることは言うまでもありません。
少し前京都近代美術館で開催していた「若きポーランド展」に行ったのですが、その時はまだポーランドに対してそこまで興味も知識も持ち合わせていない状態で行ってしまったので、展示自体はすごく面白かったのですが、今の状態でもう一度行きたいなと切に思います。
ちなみに若きポーランドというと1800年代くらいのことを指すと思うのですが、ちょうどこの時にポーランドが芸術や文学において自分たちのアイデンティティを確立しようとしていた時期でして作品から試行錯誤と混沌と革命みたいな思想が見て取れて、この展示は素晴らしかったです。
なかなか周りからは理解されず変人かテロリスト予備軍扱いされてしまう趣味ですが、ぜひ皆様も触れてみてください。
それでは本日も美味しいコーヒーと共にお待ちしております☕️